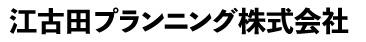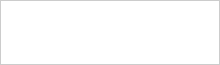不動産を購入するときや、購入したあとにはさまざまな税金がかかります。
税金のことを知らなければ、準備する金額は不動産の購入代だけだと思い、予算が足らなくなるかもしれません。
そのようなことがないように、この記事では、
- 不動産購入にかかる税金と、購入した翌年からかかる税金の種類
- 不動産購入にかかる不動産取得税の仕組み
- 不動産購入にかかる印紙税や登録免許税
を解説します。
不動産を購入する前にこの記事を読んで、税金の知識をつけましょう。
不動産購入にかかる税金の種類

不動産購入の際にかかってくる税金は、次の4種類です。
- 印紙税
- 登録免許税
- 不動産取得税
- 消費税
印紙税は、物件の売買契約を結ぶときに必要です。
所有権移転などの際にかかるのが登録免許税。
不動産を取得したときには不動産取得税、そして物件を購入する際に、その物件代に加えて消費税がかかります。
一つひとつ解説していきます。
印紙税
印紙税とは、契約書や一定額以上の領収書などの特定の文書に課税される税金です。
不動産関連では、不動産の売買契約書や建築請負契約書、土地賃貸借契約書などに規定の金額の印紙を契約書に貼付しなければいけません。
その印紙の金額は、契約書に書かれている金額により違いがあります。
この印紙税の納付方法は、決められた金額の印紙を契約書に貼り、その印紙に印鑑を押したり署名をすることです。
それにより納付したことになります。
このように印紙税を納めることにより、その文書が納税を済ませた正式な契約書となり、その取引が正式なものとなります。
また、不動産を購入し、ローンを設定する場合に、その金銭消費貸借契約書などを交わすときにもこの印紙税は必要です。
登録免許税
この不動産は誰のものかを公的に登録するためには、法務局で所有権を登記しなくてはいけません。
この登記の際に必要になるのが登録免許税です。
土地や中古住宅の場合、あなたが購入する前に、もともとの持ち主がいます。
そのため、もともとの持ち主からあなたに所有権を移転する形で登記をします。
建物を新築する場合は、所有権を設定した登記簿を作成し、それを保存することで、所有権保存登記完了です。
また、住宅ローンを利用するときにも登録免許税が課税されます。
なぜかというと購入する不動産を担保としてローンを借りるため、お金を貸す金融機関がその不動産に抵当権を設定するからです。
その抵当権設定登記の際にも登録免許税がかかるのです。
不動産取得税
不動産を取得した際にかかる地方税です。
取得した方にかかる税金となります。
不動産を有償・無償で取得にかかわらず、また、登記の有無にもかかわらず課税されます。
ただし、相続で取得した場合などは課税となりません。
不動産を取得した場合、都道府県に不動産取得税申告書を提出しなければなりません。
しかし、申告をしなくても、不動産取得後6カ月~1年半の間に都道府県から納税通知書が送られてくるでしょう。
それを金融機関に持っていき、支払えば納税は完了です。
納期は各都道府県により異なります。
ただし、一定の条件を満たした新築住宅や中古住宅は、税金の特例措置が受けられます。
その税金の特例措置を受けたい場合は、申告してください。
消費税
不動産の取得に消費税はかかるのでしょうか?
不動産自体の取引金額が大きいだけに消費税がかかるとなると、かなりの金額になってしまいますよね。
例えば5,000万の不動産に消費税がかかった場合、消費税だけで500万円の負担になります。
実は、土地の売買だけだと、消費税はかかりません。
消費税というのは、商品やサービスの「消費」に課税する間接税ですが、土地は時間が経過しても「消費」されないため、消費税の課税対象にはなりません。
しかし建物を購入したり、建てたりするときには、消費税が必要です。
土地付きの建物を購入した場合には、その建物部分だけに消費税がかかることになります。
※サービスに消費税はかかりますので、土地を購入したときの仲介手数料には、消費税はかかります。
個人から購入する中古住宅の場合は、消費税がかかりません。
購入した翌年からかかる税金の種類
不動産を購入した際にかかる税金は上記4種類だけではありません。
購入した翌年から、
- 固定資産税
- 都市計画税
という2種類の税金がかかってきます。
この2種類の税金は毎年納めなければいけない税金です。
ただし、固定資産税は固定資産の所有者は必ず納めなければいけませんが、都市計画税は、市街化区域内に土地や建物がある人だけに課税されます。
固定資産税
固定資産税は、固定資産にかかる税金で、地方税です。
その年の1月1日に土地、家屋及び償却資産の所有者として固定資産課税台帳に登録されている人に課税されます。
毎年4月から6月頃に納付書が送られてきますので、それによって支払ってください。
土地というのは宅地を始め田んぼや畑、山林なども含めます。
住居や工場、倉庫なども家屋です。
また、償却資産にも課税され、償却資材とは土地や家屋以外の事業用の資産で、例えば、構築物や、機械や装置、工具、備品などのことを指します。
固定資産税は「固定資産税評価額×税率1.4%」で計算します。
都市計画税
都市計画税も毎年払わなければいけない地方税です。
都市計画税は、都市計画事業などの費用にあてることを目的としています。
そのため、都市計画税は市街化区域に土地・建物を所有している人だけが納めます。
市街化区域とは、すでに住宅地や商業施設などが建っているエリア、もしくはこれから10年以内に優先的に市街地にしていこうと自治体が計画しているエリアです。
都市計画税の税率の計算は「固定資産税評価額×制限税率0.3%」となっており、この税率は0.3%を超えない範囲で市町村が決めます。
不動産購入にかかる不動産取得税の仕組みは?
不動産購入にかかる不動産取得税の仕組みについて解説します。
不動産取得の税率は、基本的には土地や建物の固定資産税評価額の4%です。
ただし不動産取得税にかかわる特別措置があり、住宅用の不動産であれば、税率が3%に引き下げられるという特例が適用されます。(適用期限は2024(令和6)年3月31日まで)
さらに住宅用の土地も、課税される土地の評価額が2分の1となります。
新築住宅を購入した場合
上記の減税措置に加え、一定の条件をクリアした新築住宅を購入した場合、さらに減税になります。
その条件とは、
- 住居用であること
- 住宅の延べ面積が50㎡以上240㎡以下
です。
この条件に合致する場合、新築住宅の建物部分の固定資産税評価額から1,200万円が控除されます。
つまり、「(建物の固定資産税評価額-1,200万円)×3%」となり、税額にすると最大で36万円の減税になります。
さらに、その建物が「長期優良住宅」の認定を受けると、控除額が1,300万円までに増えるのです。
土地部分も一定の要件を満たせば、さらに減税措置が受けられます。
土地の不動産取得税の計算式は「((土地の固定資産税評価額×1/2)×3%-軽減額」です。
この計算式にある「減税額」とは、
- 4万5千円
- (土地1㎡あたりの固定資産税評価額×1/2)×住宅の課税床面積の2倍(200㎡が限度)×3%(税率)
の、いずれか高いほうです。
土地を取得してから3年以内に住宅を新築などの条件に合致すると、この減税措置が受けられます。
中古住宅を購入した場合
中古住宅の建物部分の減税措置については、建物部分の固定資産税評価額から、築年次ごとに決められた額を控除するとなっています。
その控除額は以下のとおりです。
| 新築された日 | 控除額 |
| 1997年4月1日以降(平成9年) | 1,200万円 |
| 1989年4月1日(平成元年)~
1997年3月31日(平成9年) |
1,000万円 |
| 1985年7月1日(昭和60年)~
1989年3月31日(平成元年) |
450万円 |
| 1981年7月1日(昭和56年)~
1985年6月30日(昭和60年) |
420万円 |
| 1976年1月1日(昭和51年)~
1981年6月30日(昭和56年) |
350万円 |
| 1973年1月1日(昭和48年)~
1975年12月31日(昭和50年) |
230万円 |
| 1964年1月1日(昭和39年)~
1972年12月31日(昭和47年) |
150万円 |
| 1954年7月1日(昭和29年)~
1963年12月31日(昭和38年) |
100万円 |
※東京都の場合
この措置が受けられる条件は
- 住居用であること
- 住宅の延べ面積が50㎡以上240㎡以下
という、新築住宅を購入した場合の条件と同じ条件に、
- 1982(昭和57)年1月1日以後に新築されているか、一定の新耐震基準を満たすもの
という項目も加わります。
不動産取得税がかからない場合もある
不動産所得税が非課税となるケースもあります。
それは、以下の場合です。
- 公共的な目的に供される不動産の取得
- 相続による取得
- 法人による不動産の合併や分割
- 2年以内の債権消滅による譲渡担保財産の設定者への移転
相続による不動産の取得では、不動産取得税は非課税になりますが、不動産取得税が課税されてしまうケースもあります。
代表的な3つのケースを紹介します。
1:生前贈与の場合
2:法定相続人以外が遺言書により特定遺贈*を受けた場合
3:死因贈与**を受けた場合
*特定遺贈とは、特定の財産を指定して相続させることです。
**死因贈与とは、「私が死んだらこの土地をあげる」というような、死亡による贈与契約です。
次の場合にも、不動産取得税は課されません。
- 取得した土地の価格が10万円未満の場合
- 取得した家屋の価格が12万円未満の場合
- 建築した家屋の価格が23万円未満の場合
不動産取得税の非課税の申告は自分自身で申告しなければいけません。
相続などにより不動産を取得した場合、管轄の税事務所にあなた自身で申告に行ってください。
不動産購入に印紙税や登録免許税はどのくらいかかる?
不動産購入の際に印紙税や登録免許税がかかるという解説をしましたが、実際にはどのくらいかかるのでしょうか。
印紙税は、契約金額によって税額が変わりますので、契約金額によっての印紙税をリストにしました。
登録免許税は、税額の計算式がありますので、それを紹介します。
また、現在印紙税と登録免許税は軽減措置がされており、そのことも一緒に解説します。
印紙税の費用
印紙税の費用は、契約書に書かれている金額により、税額が異なります。
不動産売買契約書の印紙税は、記載金額が10万円を超え、平成26年4月1日から令和4年3月31日までの間に作成されるものについては軽減措置が講じられます。
具体的には以下のとおりです。
| 契約金額 | 本則税率 | 軽減税率 |
| 10万円を超え50万円以下のもの | 400円 | 200円 |
| 50万円を超え100万円以下のもの | 1千円 | 500円 |
| 100万円を超え500万円以下のもの | 2千円 | 1千円 |
| 500万円を超え1千万円以下のもの | 1万円 | 5千円 |
| 1千万円を超え5千万円以下のもの | 2万円 | 1万円 |
| 5千万円を超え1億円以下のもの | 6万円 | 3万円 |
| 1億円を超え5億円以下のもの | 10万円 | 6万円 |
| 5億円を超え10億円以下のもの | 20万円 | 16万円 |
| 10億円を超え50億円以下のもの | 40万円 | 32万円 |
| 50億円を超えるもの | 60万円 | 48万円 |
登録免許の費用
登録免許税額は不動産の固定資産税評価額×税率で計算されます。
この税率は登記の種類ごとに決められています。
売買による土地の所有移転登記の場合、税率は2.0%です。
相続による土地の所有権移転登記は0.4%。
新築住宅を取得した場合の住宅の所有権保存登記の税率は0.4%。
中古住宅の所有権移転登記は2.0%です。
相続の住宅の所有権移転登記は0.4%。
これが原則です。
しかし、現在(2021年9月)不動産登記にかかわる登録免許税は、軽減措置の特例を受けられます。
例えば、土地の売買で所有権が移転した場合の移転登記だと、2.0%だったのが1.5%になります。(2023年3月31日まで)
新築住宅の保存登記の場合は0.4%が0.15%に。(2022年3月31日まで)
中古住宅の移転登記だと2.0%が0.3%になります。(2022年3月31日まで)
それぞれ適用条件はありますが、かなりお得になっています。
まとめ
不動産購入時にかかる税金の種類には何があるのか、その仕組みや費用について解説しました。
不動産を購入する際には、税金分も予算に入れておきましょう。
不動産購入はさまざまな税金がかかり、減税の措置を受けようと思っても少し複雑ですよね。
「この不動産を取得したらどのくらい税金を払わないといけないのかしら」とお困りの方は、ぜひ一度江古田プランニング株式会社にご相談ください。
専門知識を持ったスタッフがわかりやすくご説明いたします。
江古田プランニング株式会社
TEL:03-4405-2458
営業時間:10:00~18:00
定休日:水曜日